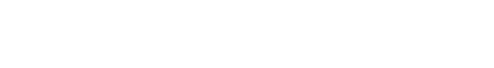所長あいさつ

グリーン科学技術の深化・進化・開花、そして、グリーン社会創生へ
現在、世界的な環境悪化や地球温暖化の影響が、あらゆる生物の生存に深刻な被害を及ぼす可能性があることは広く認識されています。これらの課題を解決するためには、さまざまな先端研究を融合させた学際的なアプローチが不可欠です。静岡大学グリーン科学技術研究所は、このような社会的・環境的課題に対応可能な、ハイテク集約型の科学技術を構築することを目指して、2013年4月に設立されました。その後、2015年には持続可能な開発目標(SDGs)が、2019年にはカーボンニュートラル(CN)が注目されるようになり、本研究所はこれらの課題に先駆けて取り組む組織としての位置づけを確立しました。
間瀬 暢之
G研の第1期から第3期の歩み(2013~2021)
第1期から第3期(2013~2021)では、朴所長のリーダーシップのもと、グリーンエネルギー研究部門、グリーンバイオ研究部門、グリーンケミストリー研究部門の3部門と、これらを技術面から支える研究支援室が組織されました。各構成員は、基礎的かつ独創的な研究に注力し、グリーン科学技術の体系化を進めました。その結果、令和4年度の総合理系では、①教員当たり研究業績数(査読付き論文数)、②教員当たり科研費獲得件数、③教員当たり科研費獲得額において国内トップの実績を達成しました。また、国内外の関連企業や自治体との連携を深めることで、社会的責任を果たしてきました。さらに、特にアジア諸国と連携し、グリーン科学技術を世界的に展開するためのプラットフォーム構築にも取り組みました。これにより、グリーン科学技術を発展させるための基盤が整ったと考えています。
G研の第4期の取り組み(2022~2024)
私が所長を務めた第4期(2022~2024)では、これまでの財産を基盤に、「健康・食料・環境」分野における「グリーン科学技術の深化・進化・開花」を推進しました。深化は「探究の深化」、進化は「学際研究の展開」、開花は「社会実装の実現」を意味し、これらを通じて各研究者の専門性を活かしつつ、組織としての成長を図りました。また、若手研究者が活躍できるコア制度の組織づくりにも注力しました。
G研の第5期の展望(2025~2027)
第5期(2025~2027)では、静岡大学のミッション「自由啓発・未来創成」の理念のもと、構成員が一丸となってグリーン科学技術に取り組みます。特に「GII グリーン社会の構築」と「GIII 海洋研究の推進」を目的とした組織体制を構築し、静岡大学未来創成ビジョンの達成を目指します。また、階層型組織研究推進システムを導入し、試行と改善を繰り返しながら、持続的な研究体制の発展を図ります。さらに、「教員の研究における質の保証」をデータに基づいて評価するとともに、研究に集中できる環境を整備してまいります。
静岡大学グリーン科学技術研究所は、これからも社会的・環境的課題の解決に向けて深化・進化・開花を続けていきます。
卓越研究コア
グリーンエネルギー研究コア(Green Energy Research Core)
・メタン生成菌・白色腐朽菌・微生物複合系・環境触媒・微生物燃料電池
二酸化炭素排出削減、カーボンニュートラルの実現、温暖化防止、日本のエネルギー自給率向上を目指して、微生物複合系および化学触媒を利用した新たなエネルギー生産技術の創成と産官学連携による社会実装を推進します。
木村浩之・加藤知香・新谷政己・平井浩文・二又裕之
(SDGs7(エネルギー)・9(技術革新)・11(持続可能))
グリーン分子研究コア(Green Molecular Research Core)
・食糧・環境ストレス・ストレスマネージメント化合物・グリーン農作物生産・気候変動
気候変動などの環境ストレスに対する耐性を強化した農作物の生産性向上を目指し、分子レベルでのストレスマネージメント化合物の探索および新たな創出に取り組み,環境ストレスを低減するための新たな分子メカニズムを明らかにします。
大西利幸・竹内純・道羅英夫・原正和・山下寛人
(SDGs13(気候変動)・2(飢餓)・15 (陸の豊かさ))
グリーンAI研究コア(Green AI Research Core)
・マルチモーダルAI/IoT・省エネルギーAI・スマート農業・漁業・スマート医療・工業
人工知能技術の環境負荷を最小限に抑えつつ、その性能と効率を最大化することを目指すだけでなく、グリーンAIを活用した環境問題の解決や持続可能な社会の実現に向けた応用研究を進めています。
峰野博史・本橋令子・一家崇志・狩野芳伸・山本泰生
(SDGs13(気候変動)・7(エネルギー)・11(持続可能)・15(陸の豊かさ)・14(海の豊かさ))
次世代研究コア
新エネルギー研究コア(Alternative Energy Research Core)
・宇宙エネルギー利用・ATP合成・光流体計測・
地球規模の気候危機下で食料危機のパンデミックが懸念される中、ゲノミクスに基づいて植物の遺伝的改良・改変を行い、地域の環境に適した遺伝子型を持つ作物を選定・育種する。
松井信・佐野吉彦・水嶋祐基
(SDGs7(エネルギー)・9(技術革新)・11(持続可能))
固体材料研究コア(Functional Materials Research Core)
・蓄電池・燃料電池・触媒・水・刺激応答
分子の構造多様性や規則配列に着目し、新物質開発と機能材料としての展開に向けた研究開発を進めています。特に電池、触媒、水浄化、外部刺激応答に関連する材料開発と産学連携を通じた社会実装を目指しています。
守谷誠・近藤満・関朋宏
(SDGs6(安全な水)・7(エネルギー)・9(技術革新)・12(責任))
分子化学研究コア(Enzyme Improvement Research Core)
・酵素・タンパク質・ケミカルリサイクル・微生物相互作用
酵素の機能解析と人工進化および微生物相互作用を研究しています。酵素とそれを生産する微生物の力を使って資源リサイクル、環境浄化および有用物質生産を効率的に行う方法を開発しています。
中村彰彦・宮崎剛亜・森智夫
(SDGs3(健康と福祉)・9(技術革新)・12(責任))
機能化酵素研究コア(Enzyme Improvement Research Core)
・酵素・タンパク質・ケミカルリサイクル・微生物相互作用
酵素の機能解析と人工進化および微生物相互作用を研究しています。酵素とそれを生産する微生物の力を使って資源リサイクル、環境浄化および有用物質生産を効率的に行う方法を開発しています。
中村彰彦・宮崎剛亜・森智夫
(SDGs7(エネルギー)・9(技術革新)・(責任)・14(海の豊かさ)・15(陸の豊かさ))
フェアリー分子研究コア(Fairy Chemicals Research Core)
・天然有機化合物・生命現象・キノコ・バイオテクノロジー・グリーンケミストリー
天然物・バイオテクノロジー・ものづくりを融合し、持続可能な社会実現に向けた科学技術を創出する。環境と生物、生物間の相互作用の解明を基盤とし、フェアリー化合物に代表される調節物質の生理機能を探究しつつ、得られた有用物質の誘導体合成研究や社会実装を目指しています。
崔宰熏・加藤竜也・間瀬暢之
(SDGs2(飢餓)3・(健康と福祉)9・(技術革新)・12(責任)・13(気候変動))